-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
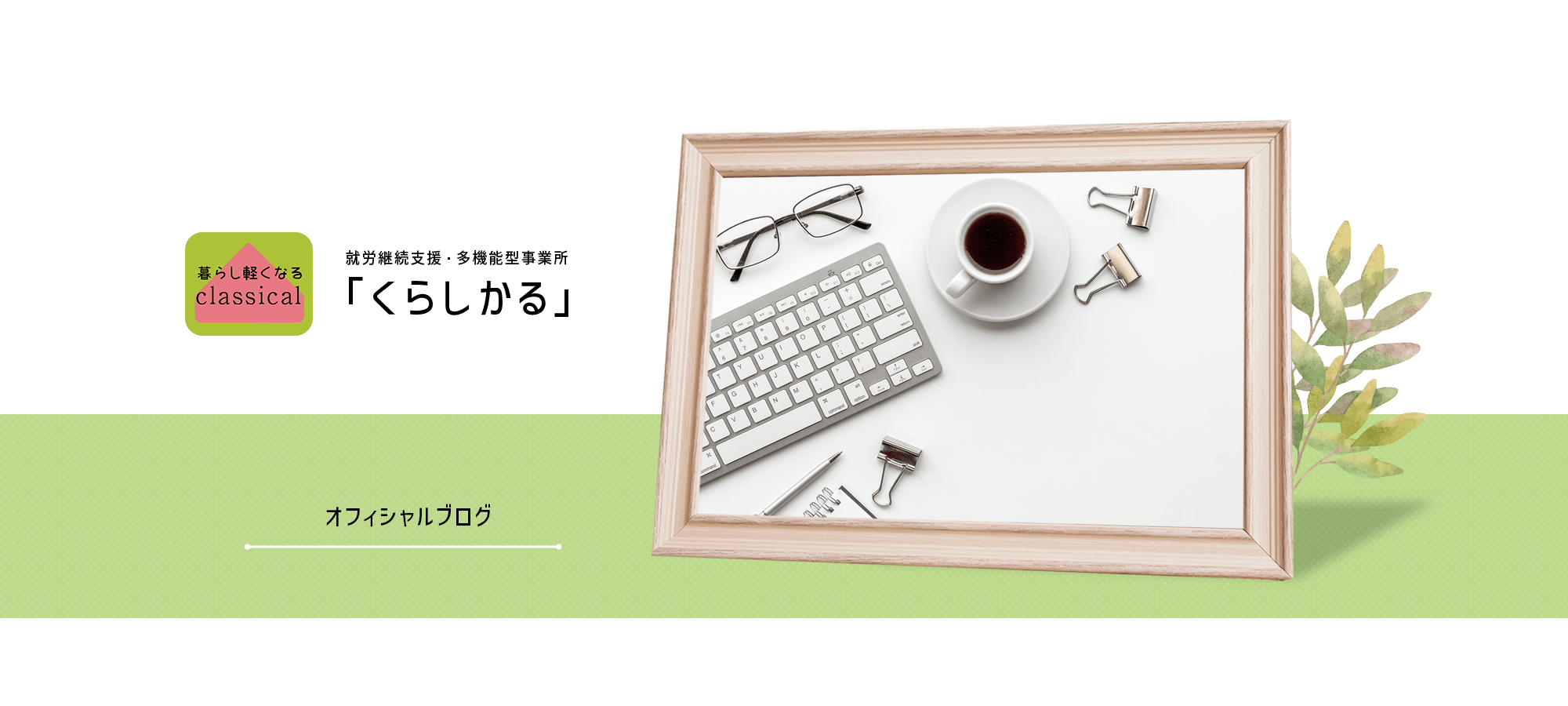
皆さんこんにちは!
株式会社RELIFE、更新担当の中西です。
さて今回は
~アセスメント~
ということで、就労支援におけるアセスメントの意味・目的・手法・活用方法について、支援現場での実例を交えながら深く解説していきます。
本人理解から始まる「働く力」のサポート設計
就労支援の現場で最も大切なことは、支援を必要とする人一人ひとりの“働く力”を正しく理解することです。
そしてその出発点となるのがアセスメント(Assessment:評価・見立て)。
「どんな支援をすればいいか?」を決めるためには、
「その人は今、何ができて、何が苦手で、どんなことに意欲があるのか?」という情報が必要不可欠です。
アセスメントとは、対象者の状況・特性・課題・強みを客観的に把握し、支援計画の立案につなげるプロセスのことです。
本人の能力やスキルの現在地を知る
職業適性や働き方の希望を把握する
生活課題・健康状態・対人関係など、就労に影響する要素を明確化
支援内容や就労目標を、本人と共有・合意形成する
📌 つまりアセスメントとは、「就労支援のスタート地点を正確に地図に描く」作業だと言えます。
障がいや疾病による特性、過去の職歴、現在の生活状況を踏まえて、 → 無理のない「就労スモールステップ」を設定可能に
「できること」と「やりたいこと」を混同すると、早期離職や自信喪失の原因に → アセスメントで現実的な可能性を冷静に見極めることが重要
チーム支援の場合、アセスメント情報が「共通言語」となる → 福祉・医療・職業訓練・家族支援など多職種連携がスムーズに
自分の強みや適性を知ることで、自己理解が深まり、意欲が高まる → 「就職したい気持ち」を「できそうな感覚」へと導く
アセスメントで得た課題や配慮事項は、職場での支援にも活用可能 → 就職後の職場理解やサポート設計に役立つ
アセスメントには「面談」「観察」「記録」「検査」など複数の方法があります。
複数を組み合わせて行うことで、より立体的な理解が可能になります。
職歴、成功体験、苦手な作業、人間関係、希望職種などをヒアリング
傾聴+質問技法が重要(「なぜ?」より「どう感じましたか?」)
実際に軽作業・PC操作・事務タスクなどを行ってもらい、観察する
注意力、集中持続、スピード、正確性、指示理解などを評価
集団活動や訓練時の様子から、対人関係やストレス耐性を把握
無言のサイン(表情・姿勢・疲労感)にも注目
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| WAIS-IV、WISCなど | 認知能力・処理速度などの知能検査 |
| VRT(職業興味検査) | 興味の方向性を把握(6領域) |
| SSTチェックリスト | 対人スキルの強みと課題を明確化 |
| 職業準備性ピラミッド | 働くための要素を5段階で整理 |
📌 検査ツールの結果は“その人を決めつけるものではない”という視点が重要です。
アセスメントで得た情報は、支援計画(個別支援計画書/就労プログラム設計)の軸になります。
| アセスメント結果 | 支援内容の設計例 |
|---|---|
| 疲れやすく集中が続かない | 作業時間を短く・休憩を多めに設定 |
| 手先が器用・細かい作業が得意 | 軽作業・検品業務などへ誘導 |
| コミュニケーションに不安あり | SST(ソーシャルスキルトレーニング)を導入 |
| 職場体験で緊張が強かった | スモールステップの実習から開始 |
📌 支援計画は「アセスメント→仮説→実践→再評価」のサイクルで改善していくことが重要です。
就労支援とは、“働く”という人生の大きな一歩をサポートする仕事。
その責任の重さと真剣さに応えるためには、一人ひとりを正確に理解する努力が必要です。
アセスメントはその第一歩であり、
支援の方向性を定め、本人の可能性を信じて伴走するための「道しるべ」となります。
| 項目 | 確認すべき視点 |
|---|---|
| 身体・精神状態 | 疾患・服薬・疲労感・通院状況 |
| 認知・スキル | 作業能力、集中力、学習スタイル |
| 生活状況 | 通勤手段、生活リズム、金銭管理 |
| 意欲・希望 | 働きたい理由、希望職種、働くイメージ |
| 人間関係 | 家族との関係、支援者との信頼感 |
![]()